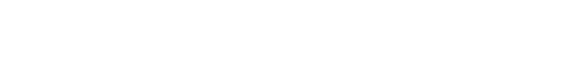神奈川県指定無形民俗文化財である室生神社の流鏑馬は、毎年11月3日に行われます。
室生神社は始め中川にあったものを天正8年、岸に移転し、その後地主神として祭られている天神の社(現在地)に遷宮したとあります。現在、中川には大室生神社があります。
祭神は建御名方尊(たてみなかたのみこと)、日本武尊(やまとたけるのみこと)、菅原道真などのほかに、明治42年3月1日無格社27祭神を合祀しています。

境内の大銀杏は樹高25m、根周り9.8m、樹齢は300年に及ぶとされています。

流鏑馬の起源は、源頼朝の石橋山挙兵の際、平家方に味方したため領地を没収され、斬刑に処されるところであった河村義秀(かわむらよしひで)が、
鎌倉で行われた流鏑馬の妙技により刑を免ぜられ、旧領に復帰できたという故事(『新編相模国風土記稿』『吾妻鑑』)によるとされています。
流鏑馬神事は「馬場駈け」「流鏑馬開始の式」「馬場入りの儀」「垢離取り(こりとり)の儀」「流鏑馬始式」「騎射」の順に執り行われ、拝殿前の「終了報告」をもって終了となります。